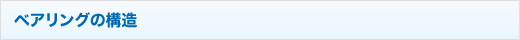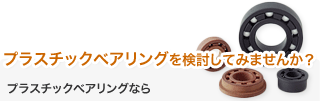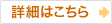ベアリングは、皆さんの生活の身近なところで様々な機械に使われています。
ベアリングには大きく分けて、ころがり軸受とすべり軸受の2種類があります。
| すべり軸受 | ころがり軸受 | |
|---|---|---|
| 形状 | 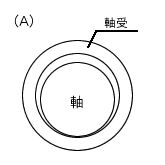 |
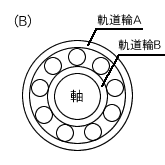 |
| 図(A)のように軸と軸受の接触ですべり運動する軸受(ベアリング) | 図(B)のように軌道輪Aと起動輪Bの間に玉やころを入れ、ころがり運動する軸受(ベアリング) | |
| 特徴 | 「あらゆる主要な軸受性能、例えば高速回転、許容荷重、寿命、剛性、大きさ、摩擦、音響など手段を講ずれば、軸受の厄介な課題はすべり軸受が解決できる資質をもっている。」(岩波書店、曽田範宗「軸受」より)
上記のように非常に優れた資質をもっており、幅広く色々な用途で使用される。 |
静摩擦係数が低く、すべり軸受より小さな力で回転運動を起こす事ができる。 また、寸法が国際規格で決まっており、色々な特徴を持った型式や寸法がある。その中から機械に適した軸受を選ぶ事ができるので設計がしやすい。 |
| 材質 |
|
|
最も一般的なころがり軸受である、深溝玉軸受けは、「軌道輪(外輪+内輪)」と「ボール(転動体)」、ボールを支える「保持器」の組み合わせで構成されています。
「外輪」と「内輪」が「ボール」を中心に別々の方向に動くことができる原理を応用して、さまざまな機械の回転や移動の部分に利用されています。